- HOME
- アトピー性皮膚炎・皮膚科
小児科
- ・ごあいさつ
- ・かぜの症状と対処方法
- ・発熱について
- ・お薬について
皮膚科
- ・ごあいさつ、疾患
- ・アトピー性皮膚炎
- ・じんましん
- ・熱傷(やけど)
- ・陥入爪(巻き爪)
- ・ウイルス性疣贅(イボ)
- ・虫刺症(虫刺され)
- ・薬疹
- ・褥瘡(とこずれ)
- ・紫外線治療
- ・紫外線による皮膚障害
診療カレンダー
■休診日
■午後休診
アクセスマップ

アトピー性皮膚炎
はじめに
アトピー性皮膚炎は乳児から成人まで10%前後と有病率の高い疾患です。乳児期を始めとした幼児期までに80%程度が発症、
成人期発症も稀ではありません。
乳児期では痒みのある湿疹が顔から始まり次第に体に下降、2ヵ月以上続く際にアトピー性皮膚炎と診断されます。
幼児期以降は乾燥肌が主体になり、頚・四肢関節部を中心に痒い湿疹が6ヵ月以上続く際に診断されます。
成人では赤ら顔やくすんだ色調の頚もよくみられます。
痒みが強く、顔をはじめとした目立つ部位に発疹がでることなどから、患者さん・ご家族の苦痛も大きいです。
健康食品や温泉療法など“完治”ないし“脱ステロイド”を唱える、いわゆるアトピービジネスは後をたちません。
こうしたことから日本皮膚科学会ではエビデンス(科学的根拠)に基づいた研究を重ね、診断と治療のガイドライン(指針)を2000年に作成、
その後も数回改訂を重ねています。その中心的な研究を行っている九州大学皮膚科のホームページは大変充実していますので、
一度ご覧いただくとよいです。
私が皮膚科医になった頃は、下着やシーツが血だらけの患者さんをよくみました。中には目の周りの発疹を激しく掻くために白内障、
時に網膜剥離を起こし、視力が低下した患者さんもいました。最近はこうした重症の方が本当に少なくなりました。
研究と治療の進歩、その普及を実感しています。


■病因:アレルギーから皮膚のバリア機能障害へのパラダイムシフト
アトピー性皮膚炎の病因は、アレルギーから皮膚のバリア機能障害へ、パラダイムシフト:劇的な変化がありました。
20年ほど前まではアレルギーに主眼がおかれることが多く、血液検査の結果のみから乳幼児期に卵・牛乳、
時には大豆製品の完全除去が勧められ、親子ともども大変な苦労をされたこともしばしばありました。
最近の研究では、アトピー素因というアレルギーの側面はあるものの、主因は皮膚の最外側の機能が弱く外からの刺激に弱い、
つまりバリア機能障害であるとされています。日本人のアトピー性皮膚炎の40%程は、角層の成分であるフィラグリンなどが、
遺伝的に弱いことことがわかってきました。健康な皮膚では、ラップのように皮膚の最外側の角層がぴっちりしていますが、
ドライスキンではすかすかしています。そのため、ほこりや細菌、衣服などの刺激が容易に下層まで入り、
炎症を起こし、水分を保つ力も低下します。さらに掻くことにより、痒みの悪循環がおこるのです。
■皮膚から入るアレルギー予防
アレルギー物質が容易に皮膚の下層に入ることは、後の食物アレルギー・気管支喘息・アレルギー性鼻炎といった、いわゆるアレルギーマーチの引き金になるとされています。 ここ数年は、新生児・乳児期からのしっかりしたスキンケアは、家族歴のあるアトピー性皮膚炎のみならず、食物アレルギーの発症も減らせる、との研究発表が相次いでいます。皮膚はアレルギー予防の最前線であるのです!
■アトピー性皮膚炎の標準治療:3本柱
アトピー性皮膚炎の標準治療は、①スキンケア、②炎症を抑える薬物治療、③悪化因子探しと対策という3本柱です。
- ①スキンケアは一番の基本です。入浴では泡立てた石鹸の泡と手で、やさしく洗いま しょう。ナイロンタオル・スポンジ・タオルなどでのこすり洗いはやめましょう。入浴後すぐ、様子で朝も保湿剤を厚くしっかり塗ることが大切です。 保湿剤は処方薬以外でも、ベビー用・敏感肌用などがお勧めです。軟膏・クリーム・乳液(ローション)を、皮膚の乾燥の程度と季節に応じて選択します。この際にフィンガーチップユニット、つまり人差し指の先端から第1関節まで、チューブから外用薬をだした量を、手のひら2枚分の面積にくらいに、厚めにしっかり塗ることが大切です。ティッシュがつく程度の感じです。
- ②薬物治療ですが、ステロイド外用剤の塗布が主体です。保湿剤と同様に、フィンガーチップユニットを頭に入れて、厚めにしっかり塗ることが大切です。ステロイド外用剤は、症状と部位に応じ適切に使えば大変有効です。ステロイド内服薬とステロイド外用剤の副作用が混同されがちですが、外用剤は適切な使用のもとでは、全身への作用はほとんどありません。症状が改善した際には、使用部位の皮膚が薄くなる、といった副作用を避けるため、外用剤の強さを下げます。2歳以上であれば、タクロリムス軟膏への切り替えを図ります。 以前は症状が出たときに治療する、リアクティブ療法が中心でしたが、最近はプロアクティブ療法の方が効果が高いことが実証されつつあります。1日2回十分量外用し、皮疹が改善したら1日1回、その後も皮疹のあった部位に週3回、週2回と段階的に外用回数を減らしてゆくのです。 少し前までは赤みのないざらざらは保湿剤のみでよい、とされていました。最近はざらざらは湿疹とみなし、“つるつる”になるように、外用薬も1回はしっかり外用するのがよいとされてきています。これは本当にツボのように思われます。触ってつるつるとなるとお子さんも掻き壊さず、ゆっくり眠れるようになります。 乳児期の口の周りの紅斑は、顔に長期のステロイド外用はよくないと、ほどほどに治療した時もありました。最近は食物アレルギー予防の観点から、できるかぎりよい状態にもってゆくようにスキンケア・外用を行っていただくようになりました。
- ③悪化要因探しと対策です。 乳幼児期は食物や汗、それ以降はほこりなどが悪化要因となることが多いです。乳幼児期の食物アレルギーについては、血液検査は偽陽性(拾いすぎてしまうこと)も多く、症状をみての必要最低限の除去が望ましいとされています。皮膚をよい状態にした上で、卵は離乳早期に開始する、という方向性もでてきました。 運動などで汗をかくことは大切ですが、そのままにすると痒くなります。着替えたり、肘などは可能であれば洗い流したり、やさしくふきとったりするとよいでしょう。 紫外線も皮膚に負担をかけるので、紫外線対策は大切です。 成人ではスキンケア用品、化粧品、毛染めなどの接触皮膚炎(かぶれ)が起こりがちです。治療への反応が悪い際には、敏感肌用製品であってもセルフテストやパッチテストをお勧めしています。
■治療目標
治療の目標ですが、完治ではなく寛解という、ほぼわからない状態にもってゆくこと、 悪化することはあっても長引かないこととされています。肌が弱い、敏感な体質として上手に付き合ってゆくことです。 情報にあふれた時代ですが、正しい情報と理解の上に、対応してゆきましょう。
(岡谷市民病院:ほすぴたる情報誌O+EN(オーエン)第19号、2014年を加筆・訂正)
皮膚科の疾患:原因と治療・対応方法
皮膚科における疾患と、原因と治療・対処方法の詳細を下記からご覧いただけます。
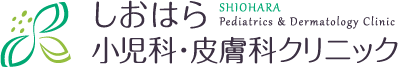
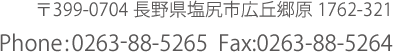

 地図を拡大する
地図を拡大する