- HOME
- じんましん・皮膚科
小児科
- ・ごあいさつ
- ・かぜの症状と対処方法
- ・発熱について
- ・お薬について
皮膚科
- ・ごあいさつ、疾患
- ・アトピー性皮膚炎
- ・じんましん
- ・熱傷(やけど)
- ・陥入爪(巻き爪)
- ・ウイルス性疣贅(イボ)
- ・虫刺症(虫刺され)
- ・薬疹
- ・褥瘡(とこずれ)
- ・紫外線治療
- ・紫外線による皮膚障害
診療カレンダー
■休診日
■午後休診
アクセスマップ

じんましん
じんましんは生涯で4~5人に1人が経験し、慢性じんましんは0.5~1%の有病率と言われる、ありふれた疾患です。 日本皮膚科学会の蕁麻疹診療治療ガイドライン、日本アレルギー学会のアレルギー総合ガイドライン2013を中心に紹介します。
■定義・症状
かゆみ伴う一過性の紅斑と膨疹が、繰り返し起こる疾患です。痒くてぽったりした赤い発疹が、出たり引いたりします。 通常一つ一つの発疹は、24時間以内に消退し、色素沈着は残しません。


■病型とその頻度
16病型に分けられています。多くは特発性(原因のわからない)じんましんです。
アレルギー性じんましんは3~5%程度と少なく、原因物質を摂取後、数分から数時間程度でおこります。
アレルギー検査をご希望される方も多いですが、血液検査のMAST 36などはアレルギー傾向を知る参考にはなりますが、
直接の原因に結びつかないことが多いです。このため問診が中心になります。
急性じんましんは感染・疲れなどを背景に広範にでることが多く、また治療への反応が悪いものの、
体調の回復とともに10日間程度で収束することが多いです。
1ヵ月以上続く際には、慢性じんましんと言います。数年続くこともありますが、ゆっくり改善することが多いです。
機械性じんましんは、こすれ・暑さ・寒さ・日光などで誘発されます。
コリン性じんましんは、入浴や運動などの発汗で細かい発疹がみられるもので、10~20代に多い傾向があります。
血管性浮腫(クインケ浮腫)は、唇や目の周りなどのぽってりした腫脹が2、3日程度続きます。
一部の降圧剤などが悪化要因となることもあり、稀に遺伝性もあります。
■悪化要因
疲労、感染、ストレス、サバなど青味の魚、アスピリンなどの解熱鎮痛剤、食品添加物、多量のアルコール摂取などがあげられます。 「サバでじんましんがでた」という方もありますが、真のアレルギー性ではなく、疲れた時に多めに食べたから、 ということもありえます。体があたたまったり疲れがでてくる、夕方から夜間に悪化する傾向があります。
■機序:起こるしくみ
アレルゲンなどが皮膚の肥満細胞に刺激を与えると、ヒスタミンなどが放出されます。 ヒスタミンは神経に働くとともに血管を拡張させ、周囲に浮腫をおこします。このために赤く膨れ、痒みを感じるのです。
■じんましんの治療、痒み対策
第一選択は抗ヒスタミン剤(H1受容体拮抗薬)の内服です。効果が乏しい時には、常用量の倍量まで増やします。
抗ヒスタミン剤はアレルギー性鼻炎などにも用いられ、一部市販薬もある比較的安全な薬剤です。
眠気が少なく効果が高い薬剤(第二世代)が好まれます。
尚収まらない際には、 H2受容体拮抗薬・ロイコトリエン受容体拮抗薬などを併用します。
副腎皮質ステロイドホルモン剤は第三選択薬で、長期投与は好ましくありません。
背景に疲れのあることが多いため、休養・睡眠は十分とりましょう。入浴は短時間ですませ、香辛料やアルコールなど、
体の温まるものは控えめにしましょう。
掻くことは痒みの悪循環をおこすのでよくありません。少し薄着にしたり、水道水程度の温度で冷やすことも一つです。
■じんましんの特殊型 ~思春期以降に増え、やはり問診が大切です。~
Ⅰ. 食物依存性運動誘発アナフィラキシー
Food Dependent Exercise Induced Anaphylaxy ( FDEIA)
小麦が60%以上で関与し、他はエビ・イカなどが原因です。原因食品を食べた後、運動ないし散歩によりじんましんが誘発されます。 時には呼吸困難・血圧低下・意識障害など、アナフィラキシー症状が伴うこともあります。 解熱鎮痛剤により増悪しやすく、運動はなくても原因食物と解熱鎮痛剤の摂取・疲れで誘発されることもあります。 予防は原因食物の摂取後、数時間は散歩や運動をしないことです。
Ⅱ. 口腔アレルギー症候群
oral allergy syndrome (OAS) : 別名 ラテックスフルーツ症候群
食物の摂取により口腔内の不快感(イガイガ感)や掻痒感が出現します。じんましんなどの皮膚症状、
稀にアナフィラキシー症状を伴うことがあります。人により果物・野菜・ナッツ・スパイスなど原因は異なります。
同じ食材でも、加熱したり缶詰では症状がでないことが多いです。
ラテックスアレルギー、白樺の花粉症と関連することもあります。
予防は原因食物の摂取を避けることです。
(岡谷市民病院祭、皮膚科展示資料、2016年を加筆・訂正)
皮膚科の疾患:原因と治療・対応方法
皮膚科における疾患と、原因と治療・対処方法の詳細を下記からご覧いただけます。
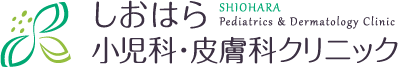
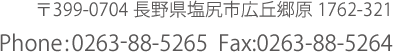

 地図を拡大する
地図を拡大する