- HOME
- お薬について・小児科
小児科
- ・ごあいさつ
- ・かぜの症状と対処方法
- ・発熱について
- ・お薬について
皮膚科
- ・ごあいさつ、疾患
- ・アトピー性皮膚炎
- ・じんましん
- ・熱傷(やけど)
- ・陥入爪(巻き爪)
- ・ウイルス性疣贅(イボ)
- ・虫刺症(虫刺され)
- ・薬疹
- ・褥瘡(とこずれ)
- ・紫外線治療
- ・紫外線による皮膚障害
診療カレンダー
■休診日
■午後休診
アクセスマップ

医院で処方された薬の知識と飲ませ方
薬は、お子さんの症状に応じて処方されます。なかなか飲んでくれないとか、すぐに吐き出してしまうなど、 薬を服用していただくうえでの苦労話をよく耳にします。薬を飲ませる意味合いを理解していただいた上で、 薬の形態と特徴を把握して、どのように飲ませるのが効果的かを一緒に考えることが、お子さんの治療を行ううえで大切になります。
■薬の飲ませ方
小児科では、咳を和らげる薬、痰を出しやすくする薬、鼻水を抑える薬、腸の働きを整える薬などが処方される頻度が多い薬剤です。
どれも病気そのものを治す薬ではありません。それぞれの症状を改善させ、和らげることで、
体力の回復を助ける働きがあります。そのことが病気の回復にもつながります。
お子さんに対する薬は、体重や年齢に適合した量が処方されます。
また、製薬会社が指定した用法、用量があるため、それらにあわせた飲み方をすることが、
薬の効き方に関わる重要な要素で、薬の効果を最大限に、かつ安全に引き出す方法です。1日3回服用の薬を1回飲めなかったため、
2回分まとめて飲ませたり、兄弟間で使い回す方法は、本来の飲ませ方ではありません。
本来の飲ませ方と異なった方法は、薬の効果が出なかったり、思わぬ副作用を引き起こすこともあります。
1日の回数や、食前、食後、寝る前など飲ませるタイミングなども様々です。自己判断で服用方法を変えないで、
医師から指示された方法で飲ませるように心がけましょう。
抗生剤は細菌感染に対する薬です。
用法、日数を守ってしっかり飲ませることが、病気の回復のために重要です。
■解熱剤について
解熱剤には、座薬と内服薬(粉薬、シロップ)があります。小児科では、アセトアミノフェンという成分の解熱剤が使われることが多いです。 同じ成分であれば、座薬でも内服薬でも解熱効果に違いはみられません。基本的に38.5度以上の発熱で、ぐったりしている、 フーフーいってしんどそう、夜間寝苦しくしている、など高熱に伴う症状がある場合に使用します。 連続して使用する場合は、6~8時間の間隔をあけて使用します。
■薬の形態について
薬には粉薬(散剤、ドライシロップ)、シロップ、錠剤、座薬などの形態があります。 お子さんの体重や年齢、体表面積などから、それぞれの体格にあった量が処方されます。 お子さんに適切な量が処方され、おうちで安全に管理していただく観点から、それぞれの形態に特徴があります。
こどもの体格にあわせて、投与量を調整することができます。また、シロップより長期保存が可能です。
ゼリーや、少量のココアと混ぜてのませるとスムーズです。袋から粉薬を取りだし、少量の水分で小さなお団子を作ります。
それをお子さんの上あごや頬の内側にこすりつけてあげると、哺乳しながら、自分で薬を溶かしながら飲むことが出来ます。
ジュースなどに混ぜて飲ませることもできますが、作り置きして保存しておくことは、薬の成分が変化することがあるので避けましょう。
また、お湯に溶かすと、成分が変性することがあるのでやめましょう。ドライシロップはお水に溶かすとシロップになるので、
粉薬が苦手な場合はお水などに溶かしてから飲ませるのが良いでしょう。
市販のスポイト、注射筒などを使って飲ませるとスムーズです。舌の上に数滴づつ分けて垂らしてあげましょう。
スプーンで離乳食が摂取できれば、スプーンにシロップを載せて、数回に分けて与えるとよいでしょう。
シロップには糖分が多く含まれているために、雑菌が繁殖しやすい欠点があります。
処方後、1週間~10日を過ぎたものは飲ませないようにしましょう。成分が沈殿しやすいので、服用直前に、
均等になるように撹拌してから服用するようにしましょう。シロップは容器にまとめて入っていることが多いので、
1回量を間違えないように取り分ける必要があります。
また、お子さんの手の届くところに置くと、
ほかの飲み物と思い込んで飲んでしまう事故が起こります。シロップ剤の管理場所にも注意しましょう。
吐き気などで口から水分などとれない時など大変有効な形態の薬です。嘔気・嘔吐や発熱時に、お子さんの状態にあわせて使用することは、
症状の緩和に役立ちます。
ベビーオイルやオリーブオイルなどを少量先端に塗ってから、肛門に入れてあげるとスムーズです。
用事2/3本とか1/2本の指示がある場合は、はさみ等で切って、先のとがった方を用います。
挿肛後、30秒ほどティッシュペーパー等でおさえてあげるとよいでしょう。
挿肛後に、形をほとんど保ったまますぐに出てきてしまった場合は、入れなおしてください。
10分以上たって便がでてきた場合は、ほとんどが吸収されたと考えられるので、
指示された時間をあけてから、症状が続く場合は使用しましょう。
「口腔内崩壊錠」と呼ばれ、唾液程度の少量の水分で溶けるため、水なしででも飲むことが出来ます。 薬を飲むのが苦手なお子さんや、吐き気がある場合などに便利です。
錠剤をかみ砕いたり、唾液で溶かして服用する錠剤です。
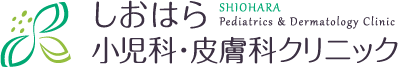
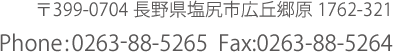

 地図を拡大する
地図を拡大する